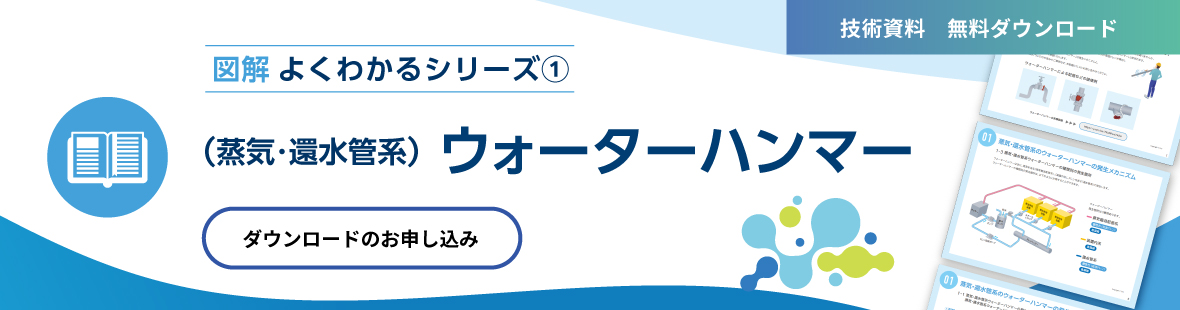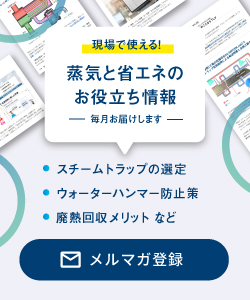- ホーム
- 蒸気のお役立ち情報
- もっと知りたい蒸気のお話
- ウォーターハンマー2 (対策総論)
蒸気のトラブル
ウォーターハンマー2 (対策総論)
発生場所と原因の特定が重要
ウォーターハンマーは、一瞬でバルブ等を破壊するほどの大きな衝撃を発生させる場合と、長い年月を経て破損に至る場合とがあり、どちらも事故に繋がることがあるので対策が必要です。
ウォーターハンマー1(発生のメカニズム)では、蒸気に起因するウォーターハンマー(スチームハンマー)に以下の2種類があることを説明しました。
このどちらが原因で起こっているのか、発生場所やタイミングによって、ウォーターハンマー対策も異なります。適切な対策を取るために、まずは発生源を特定することが重要です。
蒸気に携わる者の心得として「ウォーターハンマーが発生したらすぐにバルブを閉じよ」「バルブはゆっくり操作せよ」とよく言われます。すぐにバルブを閉じるのは蒸気の流れを止めるためですが、バルブをゆっくり開けていくことには2つの意味があります。
- 蒸気の流速を遅くする ⇒ 慣性力を弱める
- 急激なドレン発生を防止する ⇒ 単位時間当たりのドレン発生量を抑える
これらの効果によりドレンが高速で流れにくくなるため、バルブをゆっくり操作することで、1.の配管内の高速ドレンが起こすウォーターハンマーを防止できる場合があります。
蒸気の急凝縮を引き起こすきっかけとは?
しかし、「ゆっくりバルブを開けたがウォーターハンマーが発生した」「すぐにバルブを閉めたがウォーターハンマーがしばらく止まらなかった」という経験をされた方もいらっしゃいます。一体何が起きているのでしょうか。
バルブを閉めると止まるウォーターハンマー
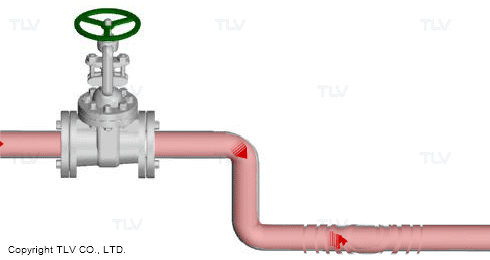
バルブを閉めても止まらないウォーターハンマー
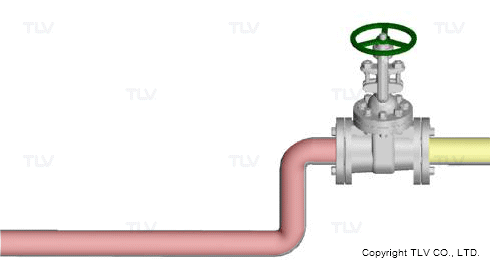
ゆっくり開けても発生したり、すぐに閉めても収まらないのは、前述の2種類のウォーターハンマーの内、蒸気が急激に凝縮しドレン同士が衝突して起こるウォーターハンマーです。
この急凝縮を起こさせるきっかけは、一言で言えば「波立ち」です。局所的な波立ちが蒸気塊を孤立させ、ウォーターハンマーを発生させます。ウォーターハンマーが発生すると、その衝撃の「揺り戻し」で再び波立ちが発生して蒸気塊を孤立させ、ウォーターハンマーを継続させるという仕組みです。
波立ちによってウォーターハンマーが発生する仕組み
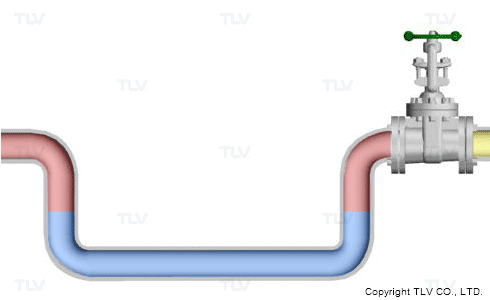
波立ちによって蒸気塊が孤立するのは、蒸気塊を孤立させるだけの「高水位のドレン」が配管内に存在しているからです。私たちの実験ではドレン水位が管内高さの約8割を越えるとウォーターハンマーの発生が始まりました。
管内のドレン水位と波立ちの関係を模式的に示すと以下のようになります。
波立ちはあるが、ドレン水位が低い場合(ウォーターハンマーは発生しない)
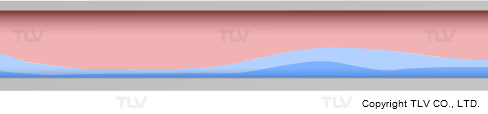
ドレン水位は高いが、波立ちが無い場合(ウォーターハンマーは発生しない)
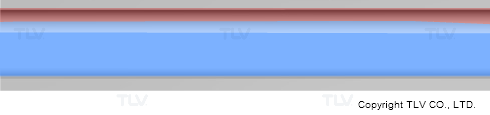
ドレン水位が高く、波立ちがある場合(ウォーターハンマー発生)
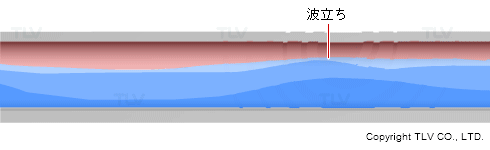
このように、ドレン水位や波立ちなど条件が重なると急凝縮のウォーターハンマーが発生することがわかります。そして、急凝縮のウォーターハンマーは配管内だけではなく、装置内でも発生することがあります。