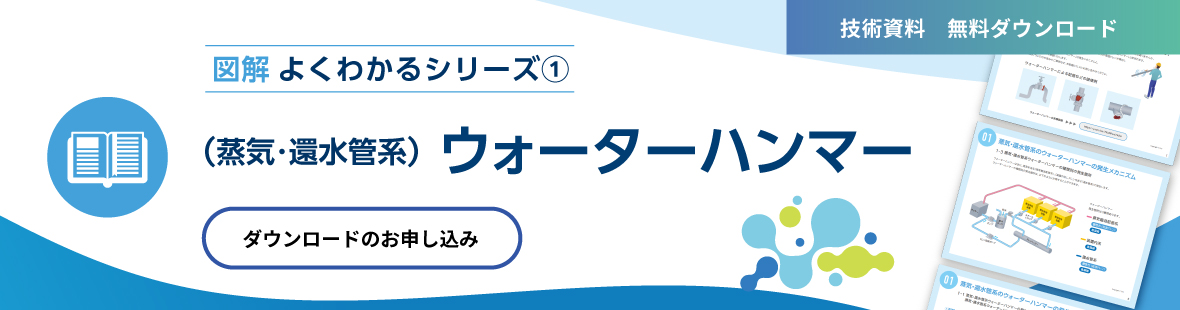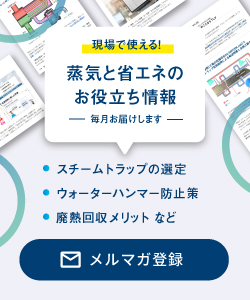- ホーム
- 蒸気のお役立ち情報
- もっと知りたい蒸気のお話
- ウォーターハンマー5(還水管の対策)
蒸気のトラブル
ウォーターハンマー5(還水管の対策)
還水管のウォーターハンマー
蒸気輸送管や装置以外に、還水管でもウォーターハンマーは発生します。還水管内は輸送対象のドレンとドレンから発生するフラッシュ 蒸気により、多くの場合、高温蒸気と低温ドレンが混在している状態であるため、もともとウォーターハンマーが発生しやすい状況にあります。
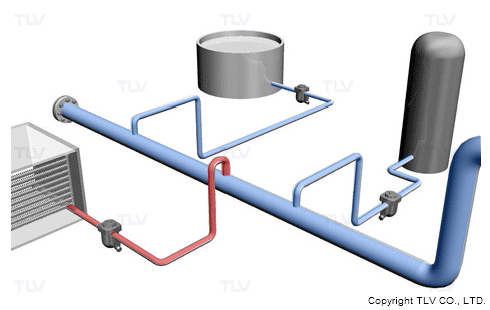
しかし、輸送対象であるドレンを排除するわけにはいかないため、還水管のウォーターハンマーには抜本的な対策がありません。軽減する(小規模に抑える)対処法しかないのです。
還水管のウォーターハンマーには多くの発生形態がありますが、基本的には全て蒸気が急凝縮するタイプのウォーターハンマーです。その一例として、装置で発生するウォーターハンマーと似た発生形態に「還水管からの逆流蒸気によるウォーターハンマー」があります。
圧力差の大きい還水管どうしの接続点やフラッシュタンクとの接続点付近で、低圧側の還水管へ高圧側のフラッシュ蒸気が逆流してウォーターハンマーを発生させる形態です。
還水管ウォーターハンマーのメカニズムと対策
チャギング
チャギングとは、還水管合流点で発生する小規模・短周期のウォーターハンマーで、chug(チャグ:エンジンなどがポッポッと音を立てること)になぞらえてこう呼ばれます。ドレンと蒸気の温度差が大きく、蒸気の急凝縮は起こるものの、大きな蒸気塊に成長しない場合にチャギングが発生します。衝撃力は小さいのですが、騒音が問題となります。
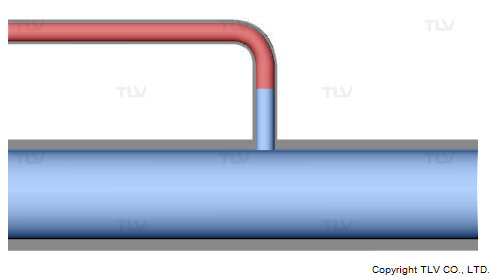
チャギング音をお聞きください
解決策
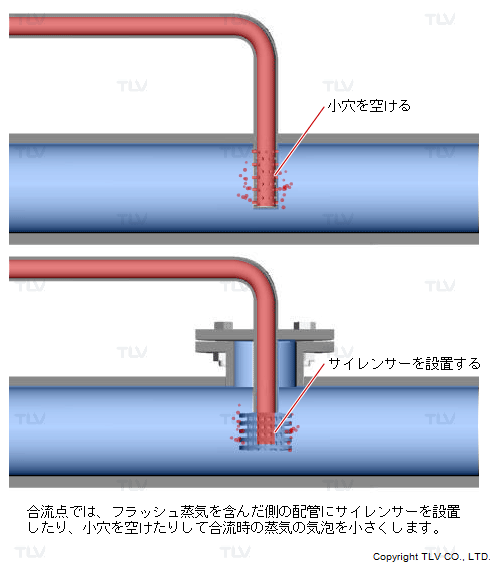
逆流蒸気によるウォーターハンマー
低温ドレンが流れている還水管が、フラッシュ蒸気の存在する還水管またはフラッシュタンクに接続されている場合に発生します。還水管の低温ドレンが脈流している場合に発生しやすく、多くの工場で見られます。ウォーターハンマーの発生場所が変化して原因究明を困難にさせることもあります。
還水管からの逆流蒸気によるウォーターハンマー
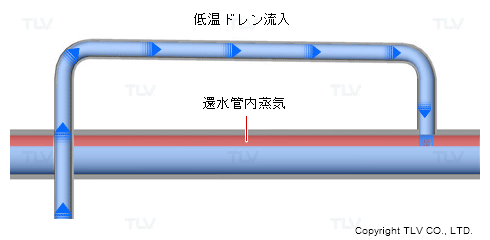
フラッシュタンクからの逆流蒸気によるウォーターハンマー
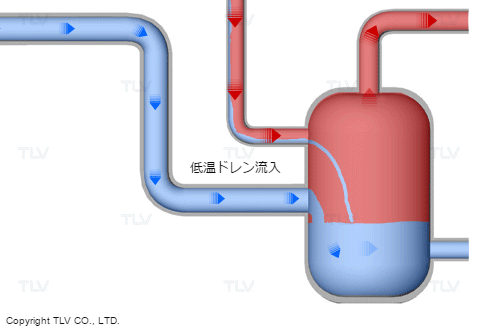
このウォーターハンマーは、還水管の低温ドレンが脈流している場合に発生するため多くの工場で見られます。
対策としては、蒸気の逆流を防止するため、チャッキバルブを設置します。但し、設置箇所やチャッキバルブの種類を間違えると、効果が半減します。
対策
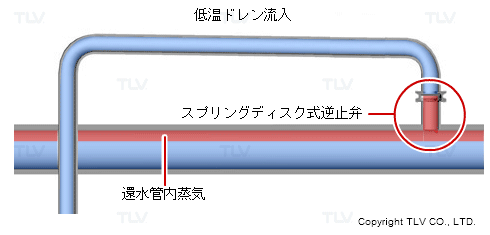
適切でない対策
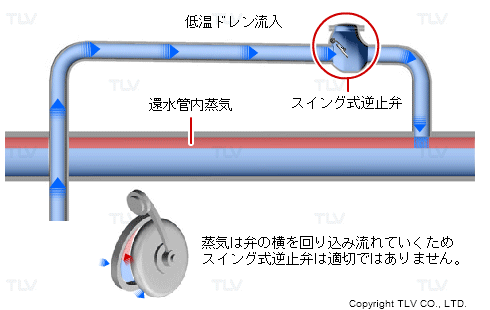
高温蒸気と低温ドレンの合流によるウォーターハンマー
高温蒸気の混じった還水管と低温ドレンの流れる還水管が、合流する箇所で発生するウォーターハンマーです。先に述べたような逆流ではなく、それぞれは順方向へ流れているのですが、合流後の配管内で蒸気塊が発生してウォーターハンマーを起こします。還水管で最もよく見られる形態です。
この場合でも、合流点から離れた場所や、合流点の上流側でウォーターハンマーが発生することがあり、原因究明を困難にさせます。
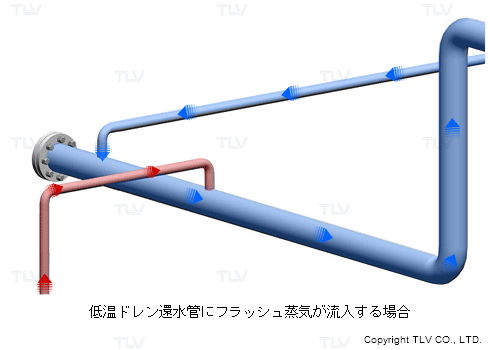
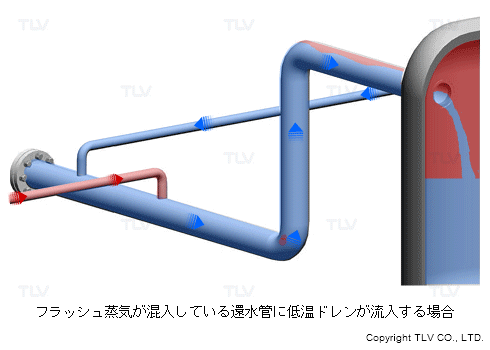
対策
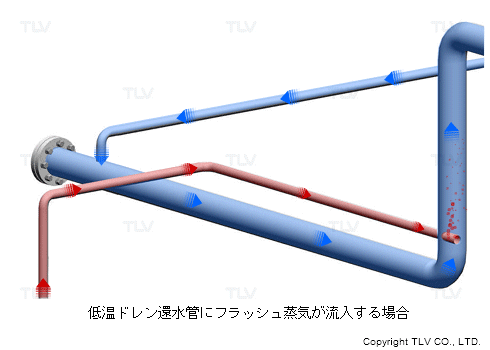
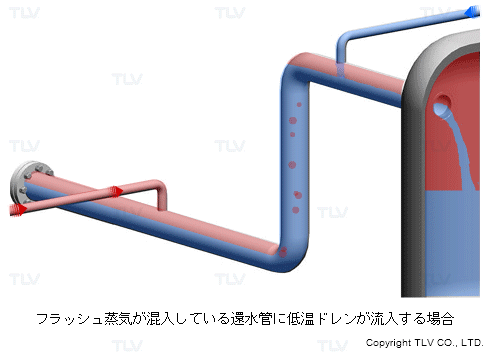
これらが代表的な3つのパターンですが、対策のポイントは共通しています。
- 蒸気塊が大きくならないようにする
- 原因となる蒸気(フラッシュ蒸気等)を遮断するか、別系統へ接続する
- 出来る限り、水平配管での高温蒸気と低温ドレンの接触を断つ
還水管で発生するウォーターハンマーは、もともと還水管自体が発生条件を備えていることもあって、発生有無や発生場所の予測が困難です。そのため、多くのケースで発生してから対策を講じることになります。更に、ウォーターハンマー発生の原因が、遠く離れた装置や季節稼動の装置の運転による場合は、より広範囲・長時間の調査が必要です。